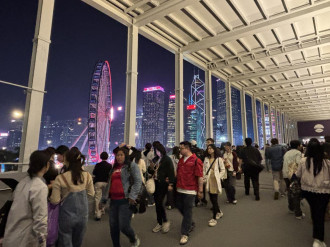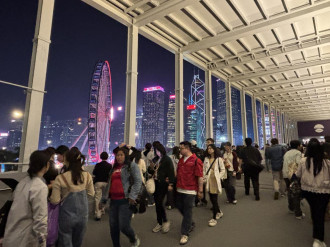香港の有名店「海皇粥店」が突如、全店閉鎖 33年の歴史に幕

香港の有名粥(かゆ)チェーン店「海皇粥店(Ocean Empire Food Shop)」が5月7日夜、突如、全店を閉鎖した。家賃高騰や「北上消費」の影響は大きく、変化する市場に対応できなかったことなどによる売り上げ減少が主な原因と見られる。香港における粥は日常食として生活に密着していることから、市民の間でも驚きの声が上がっている。
同店は1992年、蕭楚基さんと蔡汪浩さんの2人が共同で開業した。蔡さんは家族で粥店を経営していた背景がある。2人は、伝統的な粥店は衛生状態が良くないことに着目し、衛生面に気を使い、モダンな雰囲気の粥店を作ることにした。
店員の清潔感や見た目の感じを良くするため、店員には口紅を塗ることを求め、制服を配布したほか、気軽に入ることができるよう店内の装飾にも気を使った。
1999年には「五常法」というマネジメントを導入。具体的には、物品の分類や保存方法などのルールを策定した「常組織(Structurize)」、アイテムが使いやすいように整理されていることを確認する「常整頓(Systematise)」、衛生面に関するルール「常清潔(Sanitise)」、標準化された管理やプロセスをする「常規範(Standardise)」、良い習慣を身に着け、改善を継続する「常自律(Self-discipline )」を軸に据えた。
キッチンスタッフには、マスク、ネット、手袋を着用させたほか、製造後45分が経過した油條は廃棄することも徹底。その結果、2003年1月には品質管理・保証の国際規格である「ISO9001」の認証も受けた。
店舗は、2017年香港内で24店舗、海外を含める約30店舗を超えるまでに拡大した。組織が大きくなったことにより社員のキャリアパスも構築するなど、伝統的な料理を販売する一方で、現代化した企業だったことでも知られる。
しかし、コロナ禍で経営状況が暗転。コロナ禍期間中に経営状況が悪化した。収束後の香港での飲食業界は、観光客の戻りが遅かったほか、フードデリバリーが誕生し外食が減った上、家賃は依然として高額で、灣仔(Wanchai)の莊士敦道151至155号(151‐155 Johnston Road)にあった支店の店舗面積は3148平方フィートで、毎月の家賃が約40万香港ドルに上り経営を圧迫していた。
人件費も上昇し、時給を上げても依然として人手不足に陥る店もあった。香港市民が深センを訪れて消費する「北上消費」の影響もあり、飲食業界を巡る経営環境は厳しかった。
その結果、香港の飲食店では、まずは資本力のない店から閉店が続いてきたが、ついに資金力のある企業にも襲いかかった。海皇も2020年の時点では18店舗を展開してきたが、徐々に減り、2024年から2025年初頭までの8カ月間で5店舗を閉店。最後に残っていた7店舗が突如、閉店した形となった。
新規顧客として若者を引きつける必要性があったが、新しい魅力を打ち出せなかったほか、フードデリバリーへの対応も遅れた。灣仔店では、昨年の10月に45分間10香港ドルで食べ放題というキャンペーンも実施。赤字覚悟でも粥の良さを再認識してもらおうという意図があり、その反響は大きかったが、常連客を多数獲得するには至らなかった。
100人以上の従業員に対しての賃金の未払いなどが発生しており、労働者は1,500万香港ドルの回収を求めて勞工及福利局(Labour and Welfare Bureau)に訴えた。同局の孫玉●(Chris Sun)局長も「破産欠薪保障基金」という基金を通じて未払い分を補償できる見通しを明らかにしている。
2003年に発生した重症急性呼吸器症候群(SARS)では、牛頭角(Ngau Tau Kok)にある淘大花園(Amoi Garden)で多く感染者を出した。同年6月に収束したが、その5カ月後の11月に淘大花園に支店を出店。これは、「住民に対して衛生面に配慮したものを食べてほしい」という思いと、「純粋に住民を励ます」という意味からの開業で、利益を上げるだけではなく、社会貢献的な意図からの出店だった。それだけに、閉店のニュースの衝撃は香港で大きな話題となっている。
●=草かんむりに函